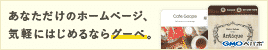寺ブログ by副住職
供養物!その3
この記事は、副住職の個人ブログ(五年ほど前の記事)からの転載です。
仕上げは・・(連続5回目)
必須供物5コ目は
☆飯食・・つまりが「ご飯」です。
ご飯は体を養うものですが「腹が減っては戦が出来ぬ」と言いますように、気力をも養うもの。楽しいご飯は嬉しい気持ちになりますね。身体を育んで心を穏やかにさせるのが、ご飯の功徳。
お釈迦さまはお腹と背中がくっつくまでの断食修行をされて、餓死寸前にスジャータ嬢が差し出した乳粥で命を取り留めました。そして心身を回復して瞑想で成道。悟りを支えた一因が「ご飯」。
仙人は霞を食べて生きるといいますが、適度な量のご飯があってこそ人は生き、健全な活動が可能です。即ち「命を養う」もと。お供えしなきゃならないワケです。
ちなみに、パンとかフレークじゃダメなのか?・・釈尊のお父さまは「浄飯王」と漢訳されているので、お米に縁が深いンだろうとは思うのですが・・後で書きますがご飯じゃないとダメな位置づけがあります。パン食の人もご飯は供えたいところ。
************
必須供物最後の6コめは
☆灯明・・明かりです。
暗闇を照らす明かりによって、人は恐怖を乗り越え、自然を克服して文明を発展させてきました。明かりとは「智慧」のもと。
さらに、明かり=光は、命のもとでもある。植物は光が無いと育ちませんし、恐竜絶滅は隕石粉塵で太陽光が遮られたことが原因と見られているそうで。人だって日に当たらないと健康を害しますね。
つまり、明かりは「智恵」ひいては「命そのもの」の象徴。仏様に供えるのは、仏の威光を以って私達のもつ暗闇を照らし給え、命を輝かせたまえ、と祈ること。仏壇にはプラス「先祖の闇をも照らしたまえ」ということ。
高野山奥の院や比叡山には「消えずの灯明」があり、お寺には「常夜灯」という基本消さない明かりがあります。それは、仏の光が絶えることなく、闇夜も私達を照らし続けるという希望。ですので「貧女の一灯」話など、灯明を献じる功徳はとてつもなく大きいとされますね。
出張などで伺いますと、仏壇の明かりを消している家庭が多いですね。火を使うローソクは目を離すと危険ですから消さねばなりませんが、昔と違って明かりにはLEDという安全便利なものが出ています。この類を使って仏壇の明かりは基本、つけておきたいものです。
それは「仏の光」でありますから。真っ暗闇な仏壇ではご先祖も意気消沈ですよ。
**********
簡単ですがお彼岸の機に、欠いてはならぬ「必須供物」をご紹介しました。
供養には必ず「事物」が必要ということ。覚えておいてほしいです。
そしてこの6種供物は、ただ「供え物」というだけの意味ではありません。そのことは次回にでも。
彼岸おわり。なんか文章が疲れてしまってるなぁ~;
**********
ブログをコピペしながら、書くと言った手前書かなにゃらんけど疲れたもう無理~、で書いてたのが如実に分かる文面で(/ω\)
ですが、とりあえず「仏前には何が必須なのか」参考にはなろうかと(;'∀')