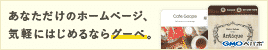お知らせ
- 2026-01(1)
- 2025-12(6)
- 2025-11(2)
- 2025-10(3)
- 2025-09(4)
- 2025-08(7)
- 2025-07(3)
- 2025-06(2)
- 2025-05(5)
- 2025-04(2)
- 2025-03(3)
- 2025-02(4)
- 2025-01(5)
- 2024-12(6)
- 2024-11(2)
- 2024-10(2)
- 2024-09(3)
- 2024-08(3)
- 2024-07(3)
- 2024-06(2)
- 2024-05(3)
- 2024-04(4)
- 2024-03(5)
- 2024-02(5)
- 2024-01(5)
- 2023-12(4)
- 2023-11(1)
- 2023-10(2)
- 2023-09(6)
- 2023-08(5)
- 2023-07(3)
- 2023-06(5)
- 2023-05(4)
- 2023-04(3)
- 2023-03(4)
- 2023-02(2)
- 2023-01(7)
- 2022-12(3)
- 2022-11(4)
- 2022-10(1)
- 2022-09(9)
- 2022-08(6)
- 2022-07(4)
- 2022-04(1)
- 2022-03(4)
- 2022-02(5)
- 2022-01(7)
- 2021-12(7)
- 2021-11(1)
- 2021-10(3)
- 2021-09(1)
- 2021-08(3)
- 2021-05(1)
- 2021-03(1)
- 2021-02(1)
- 2021-01(4)
- 2020-12(1)
- 2020-09(4)
- 2020-08(3)
- 2020-07(1)
- 2020-06(1)
- 2020-05(2)
- 2020-04(5)
- 2020-03(3)
- 2020-02(4)
- 2020-01(7)
- 2019-12(4)
- 2019-11(2)
- 2019-10(5)
- 2019-09(5)
- 2019-08(7)
- 2019-07(5)
- 2019-06(1)
太元帥→愛染王!

かつて宮中では正月7日までを神式で祝祷し、8日から14日までの後七日と呼ぶ期間を仏式(真言密教)で祈祷しておりました。
1000年続いたこの伝統は明治新政府によって壊されてしまいましたが、この祈りを後七日御修法と呼び、現在は京都の東寺に場所を移して真言各派の高僧方が天皇陛下の御衣を加持して国家国民の安寧を祈る、真言宗の最高厳儀として行われています。
後七日のこの期間、当山では太元帥明王というかつては国家鎮護の切り札とされてきた仏さまをお祀りしておりますので、御修法の祈りに重ねて微力ながら国家安寧万民豊楽を太元帥明王に祈祷しております。
本年も8日より、仁王護国般若波羅蜜多経の全読誦と金光明最勝王経の部分読誦とあわせて行じました太元帥護摩は7座をもちまして結願しました。
しかし去年もそうでしたが、太元帥の護摩の炎はどういうわけか独特な感が多いです・・あまりにコレはどうなんだろう;というのはUP止めておきますが(^^;
不穏さと不透明ぶりが加速してきた世情でありますが、国賊邪人が須らく排斥され、賢明に真っ当に生きる多くの人々が報われる世へと向かうよう、切に祈るばかりです。
また、当祈祷にご協賛くださいました心ある施主各位には感謝申し上げます。功徳力の増長をお祈りします。後ほど祈祷宝牘をお送りします。
そして、続けて愛染祈祷の開白!
毎年この時期は1週間で14座護摩を焚くので、準備祈祷片付けローテだけで目一杯、そこに寺の仕事や生活もあるのでテンテコ舞いですが今年は加えて、どうして今のタイミングなのよ⁉なアレヤこれやが(~_~;) 行者として試されてんのかなぁ~こんなにやってきても尚;
上等じゃ、やってやろうじゃないか!艱難汝を玉にすと言うが、我が如意珠にならん気合でやったるわ!この期間、室生と東寺の舎利を遥拝したがこんなところで繋がるとはww
例年よりヘビィースケジュールの後七日残り半分、がんばりますp>o</
謹賀新年!

明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いします
令和7乙巳年正月 遍照院
元朝は花巻で五段護摩による初護摩。
元日の昼からは太元堂での初護摩。
3日は新年大祈祷祭。
昨年12月から重ねて来た、願主皆様の令和7年の安全息災と繁栄吉祥の結願法会です。
・午前の部
・午後の部
午後の部は約90分のうち、炎を上げながらお加持が60分くらいか、真冬ですが内衣は汗だく(;'∀') お参りの皆様にもこの長丁場、寒行のようであったかもしれません、お疲れさまでした。
願主皆様にはお申し込みありがとうございます。祈り込めて来た祈祷は無魔結願しましたのでご安心ください。
願主各位の本年の息災と繁栄をお祈りし、法会御礼を申し上げます。
遠方等の不参拝の願主には御札を発送しました。到着までお待ちくださいませ。
当日の年頭言は文章に整理しまして、近日中にこのホームページと次回の寺報に掲載します。
1/6追記
法会のダイジェスト動画をUPしました!
※ほぼフルバージョンは、願主限定非公開動画で配信しています。希望者はご連絡を。1月10日終了。
年納めの!

28日はお不動さんの年納め法会。
一年間の加護に感謝を込めて、また、参拝者には不祥を祓って新年を迎えられますよう、不動剣によるお加持を行ないました。
信徒各位には、本年もお参りありがとうございます。佳き年をお迎えください!
納めと申しましたが、翌今日も護摩と天刑星の祈祷を修し、明日は一年の長日護摩の結願と金運守の祈祷、翌大晦日は深夜から初護摩、と祈祷には全く間断なし、であります(;'∀')
かくして新年祈祷は正月3日までお護摩を重ねて祈願しております。お申し込み各位には、お受け取りまでもうしばらくお待ちください。
万障繰り合わせの甲斐⁉

21日は納めのお大師さん。
鳴り護摩で参拝皆様にはお加持を行ないました。
も、今日は重い・・(◎_◎;)なかなか鳴ってくれない~
参拝の方々が多いと、持ち込まれるモノも重くなります・・普段お参りされない人が多かったりしますと特に(;'∀')
鳴り護摩にお参りされている方はお気づきでしょうけれども毎度、皆さんのお加持が終わった後は、鳴りが大きくなります。
ソレは、要するに重い空気が除かれた=祓われた、ということ。
眼に見えないだけで、大なり小なり人はそういう影響を蒙っている、のを如実に思わされます。
鳴りが止まった人はお帰りの際に「実は、今朝からお参りに来る足を止められるような事態がありまして・・」と。
憑いていた何か祓われたくないモノが、当山に来るのを止めようとした⁉ にもかかわらずお参りされたので、ソレが知れた上に祓いにも成った。万障繰り合わせてのお参りにはそれだけの救いがある、のを見せられました(^^; 身体が温かくなった、と仰られた方もおられました。
参拝各位には、お大師さまのお力を頂いて今年の不浄を除かれて、佳き新年迎えをされますよう祈ります!
新年祈祷開始&新御守出来!

新年祈祷の早期お申し込み(昨日までに受付)分は、本日より令和7年の新年祈祷を開白しました!
これより正月3日まで、お護摩を重ねて祈願してまいります。
新年祈祷の受付は28日までです。祈祷が始まりましたので、早くお申し込みされるほど祈祷回数が多くなり、お得です(^^
皆様のお申し込み、お待ち申し上げます!
********
また、祈祷を重ねてまいりました令和7年の新年御守、出来上がりました!
今月上旬より、この分量の御守を毎日のお護摩にかけて加持を施すこと幾度(;'∀')、お求めされる皆様の息災安全を祈り込めております。
ぜひお求めなされまして、新しい年には仏さまの一新された加持力に加護を頂かれてください!
21日の納め大師より授与します。※郵送お申し込みされている方には21日から発送します